町内で気になることがあったのでChatGPTで調べてみました
- ima3kimpoko
- 2025年8月6日
- 読了時間: 3分
まず押さえておきたい2つの視点
視点 | 何が決まっているか | 「最低●%」という数値規定はあるか | 関係する主な根拠 |
法規上(建築基準法・都市計画法) | ①容器を地面に固定すると 建築物 とみなされる
②用途地域ごとに**建ぺい率(=敷地面積に対する建築物の“占有率”の上限)**が決まる | なし – 定着の有無は「容易に動かせるかどうか」で判断され、基礎接地面の割合には数値基準が設けられていない | ・国交省通知「コンテナを利用した建築物の取扱いについて」では「適切な基礎」が必須と明示 コンテナハウス 2040 JP |
構造(地盤・基礎設計) | 地盤支持力に見合った基礎面積が必要(沈下・転倒防止) | 設計計算で決める – コンテナ重量と積載荷重 ÷ 地盤許容支持力度で算出 | ・基礎形状例(ベタ・布・独立基礎)の概説 containerworks.jp |
1. 法規側で気を付けること
1.建築確認の要否
愛川町は都市計画区域内。コンテナを物置として恒久設置する場合、10 m²超なら原則確認申請が必要です(10 m²以下でも確認不要になるのは既存建物の「増築」扱いなど限定的)。
2.**建ぺい率(敷地面積に対する建物の占有率)**の上限
愛川町第一種低層住居専用地域の例:上限 50 % 相模原市愛川町公式サイト
これは「最大値」であり 最低 ではない点に注意。
結論(法規面) 接地面積割合の 最低値 は法律で定められていません。 満たすべきは①建築確認(必要な場合)と②建ぺい率など“上限規定”です。
2. 構造面での「実務的な最低値」の考え方
2-1 計算手順(簡易)
1.荷重算定
20 ftコンテナ本体 2.3 t + 収納物 ≈ 10 t ⇒ 総重量 12.3 t(≈ 121 kN) 満載すると最大 24 t(≈ 235 kN)
2.地盤許容支持力度
住宅地の一般的な表層地盤:30–50 kN/m² が目安
3.必要接地面積
12.3 t 積載時 → 121 kN ÷ 50 kN/m² ≈ 2.4 m²
24 t 満載時 → 235 kN ÷ 50 kN/m² ≈ 4.7 m²
2-2 具体的な基礎面積比
ケース | コンテナ床面積(20 ft:≈ 14.8 m²)に対する接地面積比 |
空〜中程度の荷重(12 t程度) | 約 16 %(2.4 ÷ 14.8) |
満載に近い荷重(24 t) | 約 32 %(4.7 ÷ 14.8) |
実務目安
30〜40 % の基礎接地面積を確保すれば、一般的な地盤で満載状態まで対応しやすい。
独立基礎なら 600 mm×600 mm を6カ所(計 2.2 m²)より、1,000 mm×1,000 mm を4〜6カ所(計 4–6 m²)が安心。 (独立基礎は布・ベタより面積が小さいため地盤調査結果で再検討が必要) containerworks.jp
3. 進め方(チェックリスト)
1.用途地域・建ぺい率の確認(敷地が複数地域にまたがる場合も有)。
2.建築確認の要否を町の建築指導課で事前相談。
3.地盤調査(スウェーデン式サウンディングなど)で許容支持力度を取得。
4.基礎設計
10 m²未満・確認不要の簡易物置 → ブロック基礎でも可(ただし転倒防止のアンカー推奨)
10 m²以上・確認申請あり → 独立/布/ベタいずれかで構造計算書を添付
5.固定方法(アンカー・溶接プレートなど)を図面化し、地震・台風時の滑動・転倒チェック。
6.完成後の表面排水・防湿処理(床下が土の場合は防湿シート+押えコンクリート)。
まとめ
法律上「最低接地面積割合」の数字は存在しません。 “定着”=動かせない状態かどうかで建築物扱いが決まります。コ

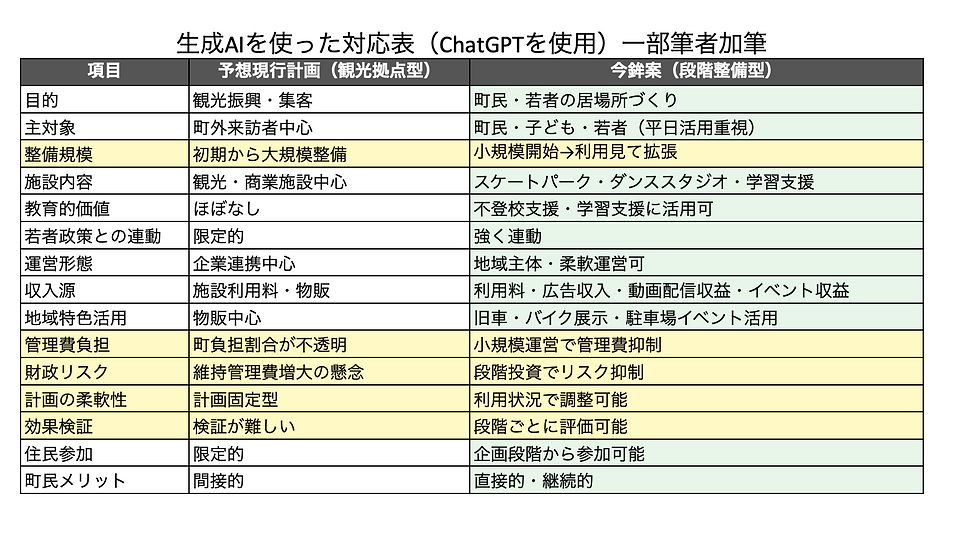


コメント