令和7年第2回愛川町議会定例会:茅孝之議員の一般質問要約
- ima3kimpoko
- 2025年10月12日
- 読了時間: 10分
注意事項以下のまとめは「会議録検索システム」の内容をもとに、ChatGPTを用いて要約したものです。本要約をもとに行われた判断や結果について、愛川ハイジの会は一切の責任を負いかねます。正確な内容は、必ず 愛川町議会公式ホームページ にてご確認ください。
以下ChatGPTによる要約→
茅孝之議員「未病対策におけるウェルビーイングを目指して」要約(議事録ベース)
1. 開会・登壇の経緯
井出一己議長が日程第2「一般質問」を宣言し、順次発言ののち、2番・茅孝之議員が登壇。茅議員は冒頭の挨拶に続き、今回の一般質問テーマを**「未病対策におけるウェルビーイング」**と明確に提示した。
2. 問題意識の提示(ウェルビーイングとは何か)
茅議員は、「あなたの幸せは何色ですか」とのラジオの問いかけを導入に用い、幸福の多様性を強調。そのうえで、ウェルビーイングを「身体的・精神的に健康な状態に加え、社会的・経済的にも良好で満たされている状態」と定義づけ、日本では1951年のWHO憲章に通底する考え方として言及した。自らの政策目標である「町民の人生を豊かにする」ためにも欠かせない基盤概念であり、町行政としてウェルビーイングを進める方策を問うとした。
3. 質問骨子の宣明
近年ウェルビーイングの注目が高まり、町民の幸福度を上げる施策の重要性が増していると指摘。町民が毎日を健康で幸せに過ごす基礎として、**心身の健康維持・増進(未病対策・健康事業)**に関する町の取組状況を問うことを通告に沿って進めるとした。
4. 町長答弁(総括とこれまでの取組)
小野澤町長は、「毎日の幸せの根は心と体の健康」と位置づけ、本町が県の未病改善宣言に基づき、健康寿命の延伸を目的に食・運動・社会参加を促す総合的施策を展開してきたと答弁。取組は特定疾患の予防にとどまらず、心身をより健康な状態へ近づけていく未病の改善を目指すものとしている。
具体策としては、
未病センターあいかわ(平成28年開設)を拠点に、健康プランに基づく町民健康講座や健康相談を実施。
健康ポイント事業の展開、地域の健康づくり事業である楽らくクラブへの支援。
健康プラザでは骨密度測定会や神奈川工科大学の協力による健康測定器を活用した生活習慣病予防教室を開催。
未病センターでは血管年齢・体組成などの測定を気軽に行い、健康意識の向上を図ってきた。
疾病予防・保健事業として、がん検診等の各種検診、乳幼児・高齢者の予防接種を実施。
高齢者の保健事業と介護予防の一体的な事業では、フレイル状態の把握と個々の健康レベルに応じた支援を実施。
以上の連続的な取組により、心身に加えて社会的なつながりの充足をもたらす、すなわちウェルビーイングの実現につながると捉えており、時世やニーズに応じて引き続き推進する考えを表明した。
5. 健康ポイント事業(仕組み・実績・評価・要望)
茅議員はまず、町長答弁にも挙がった健康ポイント事業の詳細と過去3年の応募者数推移を質問。 健康推進課長は、
各種検診・予防接種・町主催の健康講座への参加・個人目標の取組に応じてポイント付与、ポイント数に応じた参加賞・特典を授与する仕組み、
応募延べ人数は令和4年度448人、令和5年度583人、令和6年度558人であることを説明した(※一人で複数回応募があり得るため延べ数)。
これに対し茅議員は、就任初期の一般質問で特典の商品券化(あいちゃん商店街等で利用可)を提案し採用された経緯を振り返り、町民・商店街双方の満足度向上と参加意欲の喚起につながっていると評価。令和5年度から6年度にかけては微減が見られるものの、イベント参加時のポイント加算などでさらなる利用促進が可能とし、PR強化を要望した。
6. 未病センターあいかわ(機能・利用実績・周知)
続けて茅議員は、未病センターあいかわの詳細と過去3年の利用者数の推移を質問。 健康推進課長は、
健康プラザ1階「健康度の見える化コーナー」として開設され、血管年齢計・体組成計・血圧計・骨健康度測定計・脳年齢計の5機器で自己の健康チェックが可能、
希望者には保健師・管理栄養士が測定結果の説明や健康相談を実施、
利用延べ人数は令和4年度103人、令和5年度449人、令和6年度778人で、令和4・5年度は新型コロナの拡大防止対応により開設制限があったため抑制、令和6年度は制限緩和後の増加が見られる、と答弁した。
茅議員は自身の利用経験として、インボディにより部位別の筋肉量・脂肪量が把握でき、トレーニングの成果や課題が明確化できる点を評価。町内では認知が十分でなく、厚木まで測定に行く人がいるという実情を紹介し、未病センターの魅力と健康相談機能の周知不足を課題視。40代・50代など肥満・代謝への関心が高まる世代に向けた食事指導・無料相談イベントの実施など、行動変容につながるPRと仕立てを要望した。
7. 周知方法と70周年の機会活用
茅議員は、町の現行周知手段を確認。健康推進課長は、町広報紙・ホームページへの掲載、町民健康講座・健康フェスタ等でのチラシ配布、地区選出の健康づくり推進委員だよりによる広報などを説明。 特に本年度は町制70周年のため、10月26日の「ふるさとまつり」と同時開催の健康フェスタで、健康関心の有無を問わず幅広い年齢層に向けて周知を図る方針を示した。
これを受け、茅議員は周年事業の機会を最大限活用し、より多くの町民へ未病センターや健康ポイント、相談機能の周知を進めるよう要望。さらに、新規予算を要さない既存施策の連結として、未病センターの測定結果を持参して第1公園トレーニングジム(水曜はトレーナー在駐)へつなぐ「ワンパッケージ指導」の導入を提案。民間のパーソナルジムに高額費用を払うケースもある中、公的資源を束ねて身近で実用的な導線を整え、健康寿命の延伸につなげるべきと訴えた。
8. 社会的つながりの重視と「楽らくクラブ」
茅議員は、ウェルビーイングにおける社会的つながりの重要性を強調。とりわけ「孤独は人を不幸にする」との認識に触れ、町内で社会的つながりを生み出す場として楽らくクラブの意義を確認した。
健康推進課長は、楽らくクラブが児童館など身近な場所で週1回の健康体操を行い、保健師・管理栄養士による健康講話・体力測定を適宜組み合わせながら、地域での継続実施を支援する事業であると説明。実績は以下のとおり:
令和4年度:14地区/計562回/延べ9,151人
令和5年度:16地区/計697回/延べ1万1,397人
令和6年度:15地区/計668回/延べ1万1,196人
講話の具体内容については、年代に応じた動脈硬化予防、フレイル・オーラルフレイル予防、季節に応じた熱中症対策など、日常の見直しを促すテーマを扱っているとした。茅議員は、有用性の高い取組であるが認知が必ずしも十分ではないとして、さらなる周知強化を求めた。
9. 現状把握のための「幸福度・満足度」の見える化(アンケート)
茅議員は、町民が幸せであるために何をすべきかを考えるうえで、まず現状把握が重要と指摘。町では健康プラン策定に際して町民アンケートを実施しているが、健康分野の満足度や幸福度アンケート項目の追加を検討する考えがあるかを質問した。
民生部長は、健康プランの町民アンケート項目は推進委員会で検討し、従前項目を基本としつつ最近の健康情報に関する設問を適宜追加してきた運用を説明。そのうえで、次期健康プラン策定時に、健康分野の満足度などの項目を含め検討する考えを示した。茅議員は、令和11年の次期健康プラン策定(令和9~10年度に作業想定)に向け、幸福度・満足度を捉える設問の導入を重ねて要望した。
10. ウェルビーイングの要素と比較事例の示唆(議員所感)
茅議員は、ラジオ番組で紹介されていたウェルビーイングの4要素(①目標・やりがい、②感謝・人間関係、③前向きさ・楽観、④ありのまま・他者比較をしない)に触れ、とりわけ④他者比較を避け、自己の個性を尊重する点に共感を示した。ブータンの近年の幸福度低下(他国情報の流入による比較意識の高まり)に関する一般的な話題にも触れ、社会的背景が幸福感に影響するとの認識を示した。また、ユニセフ公表の子どもの幸福度に関する報道に言及し、日本では子どもの自殺率が要因の一つとされることを踏まえ、社会的要因の複合性を指摘。総じて、**「幸せな人は良い行動を生む」**との視点から、住民の幸福度を底上げする政策の必要性を強調した。
※上記は議員の所感・問題提起の範囲であり、本要約では議事録に現れる発言の趣旨として整理した(外部資料の検証や評価は付さない)。
11. 町としてのウェルビーイング指標整備・幸福度アンケートの意義(議員提案)
茅議員は、国の動向(デジタル田園都市国家構想における地域幸福度・ウェルビーイング指標の活用方針)に触れつつ、愛川町としてのウェルビーイング指標の整備を提案。指標整備には町民の幸福度アンケートが不可欠であり、町全体の幸福の現状を把握し、足りない点を施策に反映させることが重要とした。
これに対し民生部長は、全国的にも幸福度指標に基づくアンケート実施が増加している状況を踏まえ、有効性・実効性を検証しつつ、調査手法の一つとして実施の研究を行う姿勢を示した。茅議員は、町の道しるべとなる指標の整備を重ねて求めた。
12. 企業・役場への波及提案(働く人の幸福と地域の活力)
茅議員は、多くの企業でウェルビーイングが重視されている現状に触れ、そのメリットとして健康・やりがい・生産性・コミュニケーション向上・離職率低下などを挙げた。町内企業にもウェルビーイングの重要性を広くPRし、独自のウェルビーイング指標を作った企業に町からのメリットを付与する等の仕組みづくりを提案。加えて、愛川町役場自体も一つの職場であり、職員のウェルビーイングが高まれば町も幸福になるとの観点から、役場としてのウェルビーイング指標を整備するよう強く要望した。
13. 総括(議論の収束点)
本質的な論点は、既にある公的資源(未病センター、健康ポイント、楽らくクラブ、検診・予防接種、フレイル対策)を分断なく連結し、周知と参加の動機づけを高めることで、町民一人ひとりの行動変容を促し、社会的つながりを強化していく点にある。とりわけ、
健康ポイント事業のインセンティブ設計の工夫(例:イベント参加時の加点)、
未病センターの測定→相談→運動指導へのシームレスな導線(第1公園ジムのトレーナー配置日と接続)、
周年事業(健康フェスタ)等を活かした広範なPR、
楽らくクラブの実績を土台とした社会的つながりの裾野の拡大、
町民アンケートにおける幸福度・満足度項目の導入と町版ウェルビーイング指標の整備(可視化・PDCA)
が、未病対策をウェルビーイングへ橋渡しするうえでの具体的な鍵として整理された。最後に茅議員は、町内企業・役場を含め、働く人のウェルビーイングにも取り組むことで、地域全体の幸福と活力の底上げを図るべきだとして、一般質問を締めくくった。
付録:本件で示された主な数値(議事録に基づく)
健康ポイント事業(応募延べ人数)
令和4年度:448人
令和5年度:583人
令和6年度:558人
未病センターあいかわ(利用延べ人数)
令和4年度:103人
令和5年度:449人
令和6年度:778人
楽らくクラブ(地区数/実施回数/参加延べ人数)
令和4年度:14地区/562回/9,151人
令和5年度:16地区/697回/11,397人
令和6年度:15地区/668回/11,196人
まとめの一文
ウェルビーイングの実装とは、未病の視点で**「測る→相談→実践(運動・食事)→続ける」を地域に根づかせ、社会的つながりとデータによる可視化(幸福度・満足度指標)で政策を回し続けること——本一般質問は、そのための資源の束ね直しと見える化**を、町・企業・役場のそれぞれに求めたものであった。
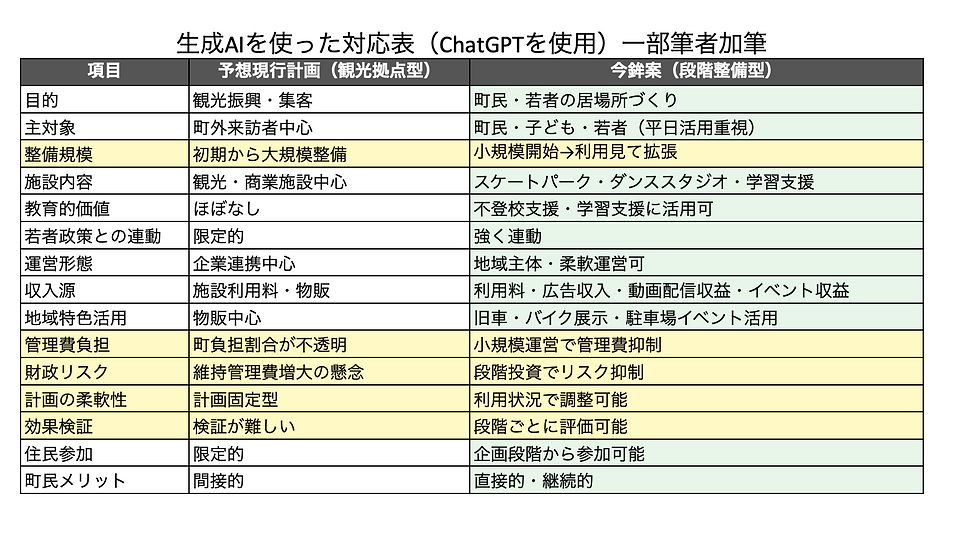


コメント