令和7年第2回愛川町議会定例会一般質問要約:鈴木信一議員
- ima3kimpoko
- 2025年10月14日
- 読了時間: 8分
注意事項以下のまとめは「会議録検索システム」の内容をもとに、ChatGPTを用いて要約したものです。本要約をもとに行われた判断や結果について、愛川ハイジの会は一切の責任を負いかねます。正確な内容は、必ず 愛川町議会公式ホームページ にてご確認ください。
以下ChatGPT
以下は、令和7年第2回愛川町議会定例会における**鈴木信一議員(日本共産党愛川町議員団)**の一般質問(3項目)の内容を、やさしく聞き取りやすい構成でまとめたものです。発言趣旨・答弁の要点・論点と今後の宿題(フォローアップ)をセットで整理しています。
1️⃣ 地域公共交通計画の策定
1-1. 鈴木議員の問題提起
路線バスは住民の主要な移動手段だが、全国的な運転手不足や需要減(テレワーク等)で減便・廃止が進み、社会問題化している。
本町でも「本数が減った/最終便が早くなった」という声が寄せられている。
町が進める地域公共交通計画(法定協議会で2カ年策定)は極めて重要。現状・課題と住民ニーズを丁寧に捉え、将来を見据えた体系を求める。
県立あいかわ公園や旧半原水源地跡地の観光拠点(観光連携拠点づくり事業)等、車を持たない人でも行けるアクセスルートの検討を要望。
既存の町内循環バスの利用促進が重要。現利用者だけでなく老人クラブ等へのヒアリングを通じた潜在需要の掘り起こしを提案。
バス停の屋根・ベンチなど、待ち環境の改善も重視。
1-2. 町長・担当課答弁の要点
現状と課題
全国的な厳しさの中で、本町は路線廃止までには至っていない。
利用者数はコロナ前比で約1割減。
減便率は12.6%(県平均15.3%より小さい)。
路線バス+町内循環バスで広くカバー。自宅~バス停距離への満足度は高め。
利用者ヒアリングでも満足・やや満足が過半。
免許返納の広がり等で将来の公共交通ニーズは一層高まる見込み。
リニア中央新幹線開業を見据え、相模原・橋本方面への新たな移動需要も把握。
調査の実施
町民アンケート:16歳以上から無作為抽出2,500人→783人(約31%)回答。
利用者ヒアリング:1/24(金)6時~21時、半原・愛川バスセンター・一本松の3か所で133人。
あいかわ公園方面の要望
接続希望の意見3件を把握。
ただし愛川・高峰ルートは1周25kmの長大路線で、さらなる延伸は困難。
循環バスに限らず、多様な輸送資源の活用や関係団体連携を含め検討。
法定協議会の進め方
9~11月に施策案協議を2回程度、2月にパブコメ反映を1回程度。
原則公開・傍聴可(議事運営に支障がない限り)。
その他
**待合環境(屋根・ベンチ等)**の課題提起は重く受け止める。
住民アンケート・ヒアリングを継続し、持続可能な体系を計画化。
1-3. 論点と今後の宿題
路線維持と減便影響の最小化:需要回復策(ダイヤ調整、乗継利便、情報発信)を検討。
観光拠点アクセス:あいかわ公園・旧水源地跡地へのシャトル・オンデマンド型・実証運行の是非。
高齢者・免許返納層の足確保:デマンド交通/乗合タクシー/地域ボランティア輸送等の組合せ。
待合環境整備:日よけ・ベンチ・雨よけの重点整備箇所選定。
広域連携:リニア見据え橋本方面との接続・広域ICカード連携など。
住民参加:法定協議会の公開性確保、パブコメの実効性向上。
2️⃣ 高齢者の外出支援(かなちゃん手形 → かなちゃんパス)
2-1. 鈴木議員の問題提起
神奈中「かなちゃん手形」制度変更が高齢者に大きな驚きと落胆を招いている。
これまでの安価で分かりやすい仕組みから、IC定期方式・高額化への移行で、年金生活者の負担が急増。
価格抑制の強い要望とともに、自治体トップ主導の広域的な働きかけを提案。
高齢者が外出すれば地域消費が生まれ、地域経済にプラス。外出抑制は地域経済の停滞に繋がる。
東京都のシルバーパス値下げの例も紹介し、公共交通の社会的役割を再確認。
2-2. 制度の整理(現行→新制度)
現行:かなちゃん手形(紙)
対象:69歳以上。
価格:3か月3,500円/6か月5,900円/1年10,800円。年4回販売(3・6・9・12月)。
利用:乗車時100円自己負担。
町の助成:当該年度70歳以上に1年券半額(5,400円)助成(6月or9月販売分)。
利用者数:R5=1,230人/R6=1,269人(増加傾向)。
※3年前に購入可能年齢を69歳以上に引き上げ(以前はより若年から可)。
新制度:かなちゃんパス(IC定期方式)
販売開始:R7.3/10。
価格:1年54,000円/6か月28,500円/3か月15,000円。
随時購入可、乗車時の自己負担なし、払戻し可。
現行手形はR7.8月末で販売終了、最終販売(R8.6月有効期限まで)に延長措置。
背景:運転士不足・運営コスト上昇等による経営の厳しさ(神奈中)。
2-3. 町の対応・答弁の要点
R6(昨年)10月の神奈中からの見直し報告を受け、R6.11に現行延長・新制度価格抑制の要望書を厚木市・清川村と共に提出。
その結果、現行手形の販売延長は実現。ただし価格抑制は反映されず。
助成継続が難しい理由:払戻し可となると、助成額を含む返金が起こり得るが、神奈中側で助成対象者の識別ができない。したがって補助制度に不適合。
今後の外出支援:タクシー利用券、電動アシスト三輪自転車助成、住民ボランティア/民間取組等、多様な支援策を続け、ニーズ変化に応じて見直し。
広域連携:厚木市・清川村に加え、他市(相模原、平塚、伊勢原、秦野等)とも情報交換・連携を視野に、神奈中への働きかけを継続。
町長所見:物価高の中で住民支援の必要性は認識(例:地域振興券)。ただし財源制約と払戻し方式により、直接助成は困難。それでも広域的に別角度から要請していく。
2-4. 住民の声(鈴木議員の聞き取り・署名活動より)
年54,000円の一括負担は年金生活者には過大。
通院・施設訪問などバスしか足がないという切実な実態。
「手形なら往復200円で外出できた」→外出機会の縮小が懸念。
2-5. 論点と今後の宿題
価格水準の妥当性:高齢者の社会参加・健康維持の公共的効果をどう評価するか。
助成の技術的課題:払戻し制度と公費投入の整合。IC側の属性フラグや払い戻し時の精算ロジック構築等、事業者との制度設計が鍵。
代替支援の拡充:タクシー券の配分・対象・上限、買物・通院への目的特化支援の検討。
広域・共同交渉:複数自治体での一括協議や広域ファンド的支援の可能性。
需要創出との両輪:公共交通の利用促進(ダイヤ・案内・乗継・ICポイント)で運賃以外の価値を上げる工夫。
3️⃣ 女性職員の管理職登用
3-1. 鈴木議員の問題提起
女性が政策立案・意思決定に参画することは、新しい発想を生み、組織活性化に資する。
現状確認:令和4年度の現状値22.9%(第3次男女共同参画基本計画の基準)に対し、今年度は22.4%で0.5ポイント後退。国の**目標30%(令和11年度)**に向け、課題整理とてこ入れが必要。
配置の偏りも問題。民生部が71.4%と突出、建設部は0%。全国的にも福祉・教育等に偏在する傾向があり、首長から遠い権力中枢領域での登用が進まないと女性の視点が政策決定に反映されにくい懸念。
採用段階からの底上げが必須。直近3年の採用試験の受験者に占める女性比率が低下傾向(R4=26.9%→R5=23.9%→R6=20.4%)。すそ野が縮むと中長期の女性幹部育成が一層困難に。
3-2. 町長・総務課答弁の要点
登用の基本姿勢:能力・適性の総合評価で、意欲と能力ある職員を登用(性別・年功で一律にせず)。
今年度の昇格:専任主幹1/主幹2/副主幹1を女性で登用。
女性管理職比率:22.4%(昨年度比**+0.3pt**)。
キャリア・リターン制度導入(本年度)により、退職者の再採用を可能化。女性1名を5月に採用。
男性の育休等も取りやすい雰囲気づくりで、男女とも事情に合わせた働き方を推進。
部門別割合(町長事務部局、4/1現在)
民生部:71.4%
環境経済部:9.1%
財務部:7.7%
総務部:6.3%
建設部:0%
育成施策:本年度、新たに**「女性職員のためのキャリアデザイン研修」を実施予定。女性管理職が講師となり経験共有・WLB意見交換**を行い、若手女性の不安解消と前向きなキャリア形成を後押し。
採用試験の女性比率:R4=26.9%/R5=23.9%/R6=20.4%(低下を把握)。
3-3. 論点と今後の宿題
数値目標に向けたロードマップ:22.4%→30%(R11)へ、年次KPIと部門別KPIを設定。
配置の偏り是正:建設・総務・財務・環境経済等、中枢・基幹部門での育成配置を計画的に。副主幹→主幹→専任主幹の多様なローテーションを設計。
採用フェーズからのテコ入れ:女性志願者比率の回復(説明会・インターン・職場見学・ロールモデル提示・奨学金返還支援等)。
両立支援の深化:育休・短時間勤務・在宅勤務の柔軟運用、職場の代替体制整備。
管理職予備群の見える化:メンター制度、タレントレビュー、越境学習や副業・研修の選択肢拡大。
評価と透明性:評価基準・昇任プロセスの可視化で納得感と挑戦意欲を高める。
まとめ(全体所感)
公共交通では、減便の影響を抑えつつ、将来ニーズ(免許返納・リニア開業)に応える持続可能な設計が焦点。観光アクセスや待合環境の改善、住民参加の仕組み化がカギ。
高齢者外出支援は、制度の高額化と払戻し可という新条件のもと、従来型助成の難しさが浮き彫り。技術的・制度的工夫と広域連携による交渉、代替支援の拡充が次の一手。
女性管理職登用は、比率の停滞/配置偏在/採用段階の女性比率低下という三重の課題。育成の仕組み化・配置設計・採用広報を一体で回すことで、30%目標に現実味を持たせたい。
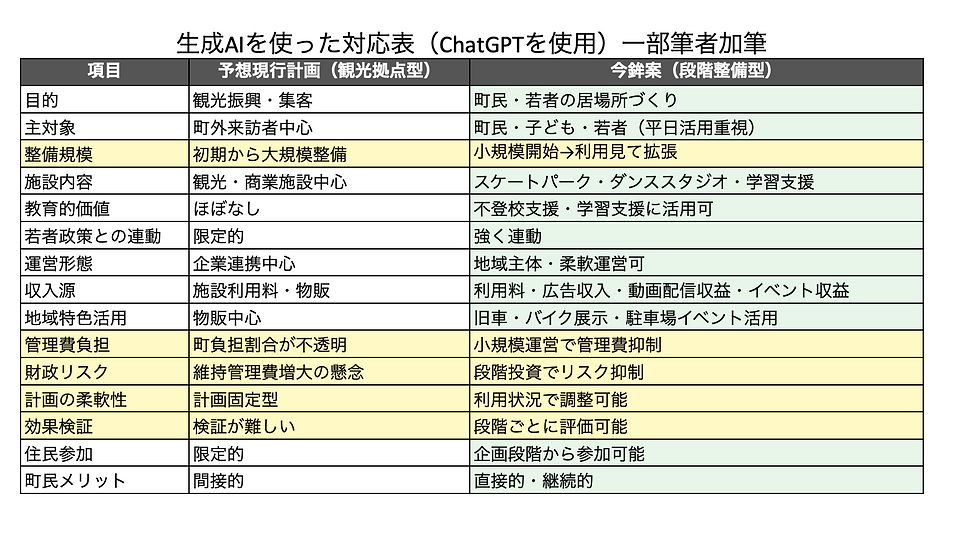


コメント