令和7年第2回愛川町議会定例会一般質問要約:花上功議員
- ima3kimpoko
- 2025年10月14日
- 読了時間: 11分
注意事項以下のまとめは「会議録検索システム」の内容をもとに、ChatGPTを用いて要約したものです。本要約をもとに行われた判断や結果について、愛川ハイジの会は一切の責任を負いかねます。正確な内容は、必ず 愛川町議会公式ホームページ にてご確認ください。
以下ChatGPT
【令和7年第2回 愛川町議会定例会】 花上功議員 一般質問「道徳教育の充実について」―ホームページ掲載向けまとめ(約1万字)
――――――――――――――――――――――――――――――
◆ 概要と位置づけ 本稿は、令和7年第2回愛川町議会定例会における花上功議員の一般質問「道徳教育の充実について」と、それに対する教育委員会(教育長・指導室長・教育次長)の答弁内容を、ホームページ閲覧者向けに読みやすく再構成したものである。原議事録の流れを踏まえつつ、要旨の明確化、項目の整理、用語の統一を図り、町の現状認識と今後の方向性をわかりやすく示すことを目的とする。なお、本文中の数値は議場での説明・発言に基づく。
――――――――――――――――――――――――――――――
【1】花上功議員の問題意識と主張の骨子 花上議員は冒頭、道徳教育を「教育の中で最も重要な柱」であり、社会秩序・国家秩序・国際秩序に連なる基盤と位置づけた。道徳の乱れが社会の乱れを生み、社会の乱れが国家や世界に波及するとの危機感を示し、現在、学校現場で顕在化する不登校・いじめの増加を前に、道徳教育の再構築が不可欠であると提起した。愛川町は「みんなが元気に明るく暮らせる町」「誰一人取り残さない町づくり」を掲げているが、そこに現れている理想と、学校現場の課題の間にギャップがある――その埋め戻しにこそ道徳教育の役割があるとした。
2015年の学習指導要領改訂により、小学校(2018年度)・中学校(2019年度)で「特別の教科 道徳(以下、道徳)」が教科化されてから6年以上が経過した。花上議員は、教科化の趣旨(いじめの解消、児童生徒の道徳性の育成)に賛意を示しつつも、「十分な成果が見えていない」との問題意識を表明。かつて日本には武士道・儒教思想・修身といった美徳が教育の根幹にあったが、戦後にそれらが否定され、精神文化の継承が途絶えたことが現代の社会的混乱を招いた一因ではないか――という歴史観を提示した。戦後80年の節目にあたり、伝統的価値の再評価と、現代的課題に応答する道徳教育の再設計を求めたのが、今回の質問の核心である。
――――――――――――――――――――――――――――――
【2】教育長答弁:道徳教育の位置づけ、推進体制、授業の方向 教育長は、道徳教育が教育基本法・学校教育法に基づくものであり、「よりよく生きるための基盤となる道徳性」を育むことを目標とする点を明確化。自己理解を深め、物事を多面的・多角的に考え、他者と共に生きるための判断力・心情・実践意欲・態度を育てる学習であると整理した。その上で、愛川町内の各学校では、学校長の方針のもと「道徳教育推進教師」を中心に重点目標・重点内容を設定し、道徳の授業を中核に、他教科や特別活動も含めた「教育活動全体」を通して道徳性を育む取組を進めていると述べた。
不登校・いじめへの具体対応としては、「命の大切さ」「他者への思いやり」を題材とする授業を実施。いじめを見て見ぬふりをしない行動や、相手の立場に立つ想像力の育成を重視し、未然防止と人間関係の改善に資する学級文化の醸成に努めているという。さらに、「自分を大切にしてよい」「多様な考えがあってよい」という価値観を共有することで、安心して学べる環境づくりを進めている点を強調。今後も「自ら考え、対話で気づきを深める“考え、議論する道徳”」を推進する方針を示した。
――――――――――――――――――――――――――――――
【3】現状データ:自殺・いじめ・不登校(町の状況と全国推移の参照) (1)自殺に関する認知 指導室長は、全国では子どもの自殺が増加傾向にあり、令和5年の小中高生の自殺者数は513人と過去最多水準で推移している一方で、愛川町内の小中学校では自殺事案の認知は「なし」と報告した。町内の状況として重大な危機は発生していないが、全国的傾向には注意を要するというのが教育委員会の認識である。
(2)いじめの認知件数 いじめ防止対策推進法に基づく定義で集計した令和5年度の町内認知件数は、小学校79件、中学校42件。自殺の企図や重大な身体損傷、金品等の重大被害、精神疾患の発症などに該当する「重大事態」は発生していない。件数は「認知の精緻化」によって増える側面もあるが、予防・早期対応・関係改善に向けた継続的な注視が必要といえる。
(3)不登校の状況 不登校は、病気・経済理由を除き心理・情緒・身体・社会的要因等により年間30日以上欠席した場合を指す。令和5年度の町内では、小学校1,688人中47人、中学校973人中119人である。花上議員は人口比換算で町内の不登校割合が全国平均より高いと指摘し、特に小学校は全国平均の約3倍に相当するとの問題意識を示した。要因として、学習意欲の低下、不安・抑うつ、生活リズムの乱れなどが挙げられ、心理的支援の必要性が強調された。
――――――――――――――――――――――――――――――
【4】道徳教育推進教師の役割:学校横断のハブ機能 花上議員の問いに対し、指導室長は推進教師の具体的役割を次のように説明した。①道徳教育の指導計画の作成、②教育活動全体での推進・充実、③道徳の授業体制の整備、④教材・図書・掲示物・資料コーナーの整備、⑤授業公開や家庭・地域との連携、⑥教員研修の充実、⑦評価の工夫、⑧授業に悩む教員の相談支援等である。すなわち、推進教師は学校全体の協働体制を整えるハブであり、授業づくりと環境整備、校内研修と連携の両面で舵取りを担っている。花上議員はこの体制を評価し、さらなる機能強化に期待を示した。
――――――――――――――――――――――――――――――
【5】「忘却」を前提とした学びの定着:柱(徳目)の必要性 花上議員は、人が本質的に「忘れる存在」であることを前提に、道徳の定着には「心の軸」「柱」の明示が不可欠だと提案した。週1回の授業では学びの保持が難しい現実を踏まえ、反復可能かつ生活場面に適用しやすい「徳目」を、算数の九九のように繰り返し確認できる学習設計が望ましいとする。ここで議員は、エビングハウスの忘却曲線に触れつつ、短期に低下しがちな記憶を「基準の明確化」と「反復」によって補強すべきだと主張した。
――――――――――――――――――――――――――――――
【6】教育次長答弁:体験と対話で「自分事化」する授業改善 教育次長は、「教え込む」道徳からの転換を示した。いじめを例に、加害・被害・傍観の立場を役割演技や場面想定で相互に体験し、対話を通じて「自分ならどうするか」を考える授業づくりを強調。多様性が前提となる社会で、他者を大切にし、同時に自分も大切にする姿勢を育むことを中核に据え、「考え、議論する道徳」を一層推進する考えを示した。ここでの要点は、価値の「理解」から、態度・行動の「習慣化」へ橋渡しするための授業デザインである。
――――――――――――――――――――――――――――――
【7】国内外の系譜:修身・武士道・Virtues(徳の書) 花上議員は、徳目を「心の座標軸」として再構築するための参考枠を、国内外の系譜に求めた。明治期の新渡戸稲造『武士道』は、英語圏で広く読まれ、後年、米国の教育改革にも影響を与えたとされる。特にレーガン政権期に、米国の教育長官(ベネット氏)が『The Book of Virtues(徳の書)』を著し、自己規律・同情・責任・友情・勤勉・勇気・忍耐・正直・愛情・信仰という10徳を提示したことは象徴的である。日本の武士道においても、義・勇・仁・礼・誠・名誉・忠義の7徳が示されている。さらに、修身の十二徳(孝行・友愛・夫婦の和・朋友の信・謙遜・博愛・修学習業・智能啓発・徳器成就・公益世務・遵法・義勇)も、生活の中で反復的に想起しやすい「基準」となり得るとした。
ここで議員は、「伝統の復古」ではなく「現代の課題に応答する再設計」である点を強調する。すなわち、歴史に学びつつも、現代の多様性・人権・個性尊重の価値観と矛盾なく共存しうる倫理枠組みを提示することが重要だという視点である。徳目は「行動の羅針盤」であり、反復を通じて初めて定着する。学校だけでなく、家庭・地域を巻き込んだ「生活接続型」の学びが鍵になる。
――――――――――――――――――――――――――――――
【8】町の教育の課題認識と改善の焦点 以上のやり取りを踏まえ、町の教育課題として次の4点が浮かび上がる。
① 学級風土の継続改善 安心して学べるクラスは、道徳教育の「土台」である。価値の教示だけでなく、日常の関わり・合意形成・トラブル対応のプロセス全体が学びとなる。担任だけに過度な負担が集中しないよう、推進教師のハブ機能と管理職のバックアップ、スクールカウンセラー等の専門職連携を含めた体制整備が重要。
② 心理的支援の拡充 不安・抑うつ、生活リズムの乱れといった不登校要因に対しては、心理的安全性の確保、セルフケアの習慣化、学校外の支援資源の活用が不可欠。個々の要因に応じたプラン(教育支援計画的アプローチ)を組み立て、教員間共有・家庭との協働を体系化することが望まれる。
③ 授業改善(体験・対話・省察のサイクル) 役割演技、ケース討議、ピア対話、ふりかえり記述、次回につなげる「小さな課題」の設定など、思考と行動が往還する授業デザインが有効。「正解を覚える」から「状況に応じて判断し行動する」への転換を促す。
④ 徳目の可視化と反復(スパイラル学習) 学年段階に応じた徳目の焦点化(例:低学年=基本的生活習慣と共感、中学年=友情・公平、高学年=責任・正直、中学生=勇気・自律・社会参画)を行い、繰り返し出会わせる。校内掲示、朝の会、保護者通信、地域連携行事など、接触機会を複線化して「生活の中で想起される仕掛け」を増やす。
――――――――――――――――――――――――――――――
【9】推進教師の活用と学校全体の運営工夫 推進教師は、教材整備・授業公開・情報共有・校内研修を組み合わせ、教師が孤立しない環境をつくる役割を担う。具体的には、①学年・教科横断の授業研究(公開・相互参観)、②優良実践の共有(ミニレポート化)、③家庭・地域との協働(ゲストスピーカー、地域ボランティア連携)、④評価とフィードバック(観点別記述、ポートフォリオ)など。これらを管理職が制度として後押しすることで、学校全体の学びが持続可能になる。
また、いじめ認知の精緻化と同時に、早期の関わり直し(リペア)を促すための「対話の型(Iメッセージ、リフレクティブリスニング等)」を校内共通言語として整えることも有効である。生徒会活動・特別活動と連動し、子ども自身が規範形成に関わる機会を設けると、当事者意識が育ちやすい。
――――――――――――――――――――――――――――――
【10】家庭・地域とつながる「生活接続型」道徳 学校で学ぶ徳目が、家庭や地域の生活場面と切り離されると、定着は弱まる。保護者向け通信で授業のキーワードを簡潔に共有し、家庭での会話を促す。地域の行事やボランティア活動と授業テーマを連動させ、子どもが「役に立てた」「ほめられた」という経験を積み重ねる。神社仏閣や地域の史跡、地域の仕事人から学ぶ「ローカル・カリキュラム」は、抽象概念を「自分のまちの物語」に変換し、学びの実感を高める。花上議員の「歴史や文化から学ぶ道徳」の趣旨は、こうした生活接続の観点からも合致する。
――――――――――――――――――――――――――――――
【11】評価と記録:行動変容を支える仕組み 道徳の評価は数値化しにくいが、だからこそ「記述」と「ふりかえり」が重要になる。観点別に短い所見を積み重ね、生徒自身のポートフォリオ(ワークシート、振り返りカード、クラスでの役割記録等)と紐づける。保護者面談・三者面談では、具体場面での行動と成長の兆しを共有し、次の一歩を合意する。評価は序列化のためでなく、行動の定着を促すための「対話の起点」であるべきだ。学校間でフォーマットを統一するより、各校の実情に応じて柔軟に設計し、推進教師が核となって改善サイクルを回すことが現実的である。
――――――――――――――――――――――――――――――
【12】花上議員の結び:伝統の再評価と町独自の創意 花上議員は結語で、修身の十二徳を列挙し、これらを「常に心の片隅に置く生活知」として再評価するよう呼びかけた。昭和が戦前を、令和が昭和を否定する――という「断絶の連鎖」を戒め、歴史から学ぶ姿勢の回復を提案。建国の歴史や神話を含む文化的教養を等身大に学び、町としても国の方針にとどまらない独自の工夫を加えた道徳教育の展開を期待して、一般質問を締めくくった。
――――――――――――――――――――――――――――――
【13】総括:愛川町の道徳教育に向けた提言ポイント 本件質疑から導かれる、実務上の注力ポイントを整理する。
① 「考え、議論する道徳」の継続推進 体験(役割演技・ケース討議)→対話→省察→小さな実践、という学習サイクルの定着。単発ではなく、学期・年間を通じた「連続性」を設計する。
② 徳目の可視化とスパイラル化 学年段階ごとに焦点徳目を設定し、繰り返し出会わせる。校内掲示・朝の会・特活・行事・家庭通信など、複数チャネルで想起機会を増やす。徳目は「禁止の羅列」ではなく「行動の羅針盤」として提示する。
③ 推進教師のハブ機能の強化 授業素材の共有、校内研修の設計、公開授業の運営、悩む教員の相談窓口、家庭・地域連携のコーディネート等。管理職が制度として支え、持続可能な体制にする。
④ 心理的支援と個別最適化 不安・抑うつ・生活リズムの乱れ等に対し、スクールカウンセラー等の専門職と連携。個人差を前提に、小さな成功体験を積み重ねる支援を設計する。
⑤ 生活接続と地域資源の活用 地域の史跡、神社仏閣、職人、事業者、市民団体等を学びに接続する「ローカル・カリキュラム」。子どもが地域の一員として役割を担い、承認を得る経験を増やす。
⑥ 評価=対話の起点 観点別記述とポートフォリオで行動変容を可視化。保護者・生徒・教員の三者でふりかえり、次の一歩を合意する。評価は序列化ではなく、成長支援のための仕組みと位置づける。
――――――――――――――――――――――――――――――
【14】おわりに 愛川町は、道徳を「教える」だけでなく、学校生活全体へと拡張し、家庭・地域との協働により「生きた学び」へと転換するステージに立っている。いじめ・不登校の背景は複合的であるが、対話・共感・自律を核に据え、徳目という「心の基準」を生活に接続し直す工夫を重ねれば、子どもたちは確かな手応えをもって「よりよく生きる力」を育むだろう。今回の一般質問は、伝統を現代の文脈で再解釈しながら、町独自の創意で道徳教育をアップデートしていくための具体的な方向を示したものと言える。教育委員会の掲げる「考え、議論する道徳」と、花上議員の提案する「徳目の明確化・反復」は、対立する概念ではなく相補的である。体験と対話で自分事化し、徳目で行動の羅針盤を持つ――その往還が、子どもたちの心に息づく道徳を育て、学級・学校・地域の文化を静かに変えていく。
以上。
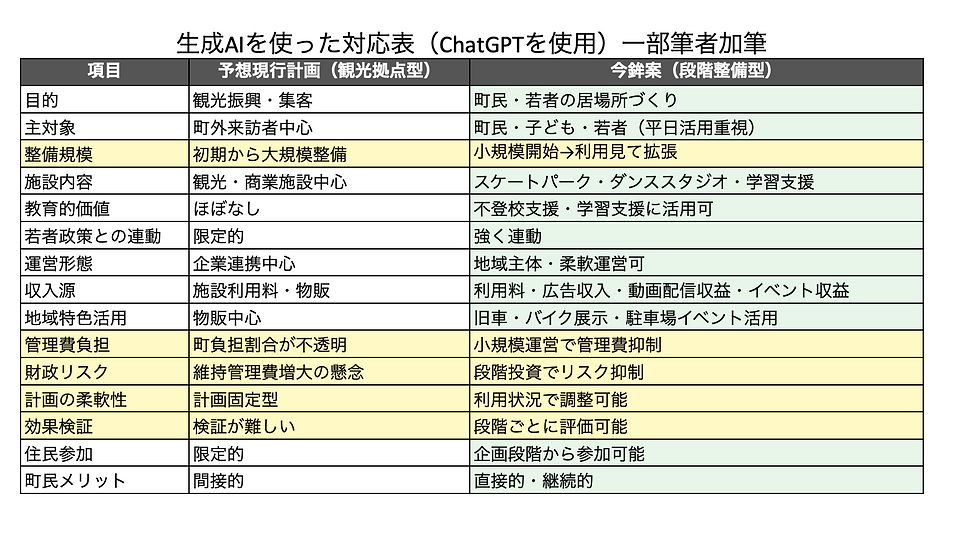


コメント