令和7年第2回愛川町定例会一般質問。岸上敦子議員の第1項目について
- ima3kimpoko
- 2025年8月31日
- 読了時間: 7分
注意事項
以下のまとめは「会議録検索システム」の内容をもとに、ChatGPTを用いて要約したものです。本要約をもとに行われた判断や結果について、愛川ハイジの会は一切の責任を負いかねます。正確な内容は、必ず 愛川町議会公式ホームページ にてご確認ください。
令和7年第2回愛川町議会定例会
一般質問 岸上敦子議員(公明党)
第1項目 地球温暖化対策について
1. 質問の趣旨と背景
今回の一般質問で岸上議員は、まず第一に「地球温暖化対策」を取り上げた。国レベルで2050年カーボンニュートラル実現、そして2030年までに温室効果ガスを46%削減するという野心的な目標が掲げられている中で、愛川町がどう対応していくかを問うものであった。
岸上議員は、これまでの施策を振り返りながら、次の2点を明確に提示した。
町がこれまで取り組んできた温室効果ガス削減の実績と具体策はどうなっているのか。
環境省が推進する「デコ活」運動に町として賛同・宣言し、今後の脱炭素施策をどう展開していくのか。
この2点を切り口に、町民の生活と直結するエネルギー施策やリサイクル事業、そして町全体の行動変容を促す広報・啓発の重要性に焦点を当てたのである。
2. 町長の答弁:これまでの取組と方向性
小野澤町長は答弁に立ち、まず町がこれまで取り組んできた施策の全体像を整理した。
2.1 公共施設の省エネ・再エネ導入
町の取り組みの中心は「公共施設の省エネ化」である。健康プラザの屋上に設置された太陽光発電設備は、町が率先して再生可能エネルギーを導入している象徴である。また役場庁舎や周辺の公共施設ではESCO事業を活用し、空調・照明設備を高効率型に更新した。さらに高圧電力の供給契約を再生可能エネルギー電力に切り替えるなど、町としても自ら温室効果ガス削減の「モデル」になる姿勢を示してきた。
2.2 補助金制度の活用
町民や事業者が直接的に参加できる仕組みとして、平成18年度からは太陽光発電設備の導入補助を開始。令和3年度以降は「スマートエネルギー設備導入費補助金」へと発展させ、家庭用蓄電池やエネファーム(家庭用燃料電池)などにも対象を拡大した。こうした支援は町民の自発的な再エネ投資を後押しする重要な仕組みである。
2.3 森林整備によるCO₂吸収源の確保
環境対策は省エネや再エネだけではない。町長は「森林の多面的機能」を重視し、計画的な森林整備を進めてきたと述べた。森林は単なる自然環境ではなく、町にとって「炭素吸収源」として不可欠な存在である。
2.4 民間事業者との連携
近年特徴的なのは「民間企業との協働」である。令和5年には不用品リユース事業を開始し、家具や家電などが再利用されている。サントリーグループと協働したペットボトルの「水平リサイクル」では、家庭から回収されたボトルを再び飲料容器に戻すことで、従来の石油由来原料に比べ約60%ものCO₂削減効果を得ている。さらに令和6年からは小型家電(パソコンなど)の回収リサイクルも開始。こうした事業は町民の生活習慣と直結し、町全体の脱炭素意識を高める役割を果たしている。
2.5 新たな取り組みとゼロカーボンシティ宣言
令和7年度には郷土資料館と愛川聖苑の照明LED化が予定されている。そして最も注目すべきは、令和7年5月1日に町が「ゼロカーボンシティ宣言」を行ったことである。これは単なる施策の一環ではなく、町が長期的に「脱炭素社会実現」に向けてコミットした大きな意思表明といえる。
3. デコ活への対応:町の姿勢
続いて町長は、クールチョイスに代わる新国民運動「デコ活」について説明した。
デコ活は「Decarbonization(脱炭素)+Eco」を由来とする造語で、生活全般のライフスタイル変革を促すもの。
平成30年に町が賛同した「クールチョイス」を継承・発展させた運動で、衣食住・移動・買物など幅広い行動分野に13の具体アクションを示している。
町としては、まずはゼロカーボンシティ宣言を町民や事業者に浸透させ、そのうえで令和7年11月を目途にデコ活宣言に切り替える方向で検討中である。
町長の答弁は、愛川町が国の政策動向を注視しつつ、町民参加型の施策を打ち出していく姿勢を明確に示すものであった。
4. 岸上議員の再質問と掘り下げ
岸上議員は一括答弁を受け、いくつかの具体的な点をさらに掘り下げていった。
4.1 補助金実績の確認
まず取り上げたのは「スマートエネルギー設備導入費補助金」の実績である。環境課長は年度ごとの詳細を報告した。
令和3年度:太陽光6件・蓄電池12件、補助額計77.8万円
令和4年度:太陽光20件・蓄電池13件、124.6万円
令和5年度:太陽光15件・蓄電池25件、170万円
令和6年度:太陽光21件・蓄電池25件、186.9万円
年を追うごとに件数・金額とも増加しており、町民の関心が着実に高まっていることを示す数字である。
4.2 民間連携による取組の成果
次に議員は、不用品リユース、ペットボトルリサイクル、小型家電リサイクルといった民間連携の成果を問うた。環境課長は具体的な数値を挙げて答弁。
不用品リユース:160件の申込、394点が再利用。
ペットボトル水平リサイクル:183トンを100%再利用し、約60%のCO₂削減効果。
パソコンリサイクル:206件申込、302台を回収。
これらは「温室効果ガス削減の一助となっている」と評価され、町民協働型施策の成果として肯定的に総括された。
4.3 省エネ家電買換え補助の提案
岸上議員は「家庭におけるCO₂削減を促すには、省エネ性能の高い家電への買換え補助も効果的」と提案。他自治体の事例を踏まえ、町でも検討を求めた。
これに対し環境経済部長は「現時点では既存施策の継続を優先しつつ、近隣自治体の先進事例や費用対効果を調査しながら研究していく」と答え、即導入には慎重ながら前向きな姿勢を示した。
4.4 第4次エコアクションプランの具体行動
議員はさらに「町が一事業者・消費者として具体的にどう行動しているか」を問う。環境課長は、庁舎照明の消灯や廃棄物分別、職員家庭での自主的エコ、学習会開催などを紹介。文具や用紙の購入に再生材を使い、会議資料を簡素化するなど、日常業務の中に削減行動を組み込んでいると説明した。
議員は「こうした地道な取り組みを評価する」としつつ、庁内にとどまらず町全体に広げる重要性を強調した。
4.5 区域施策編の必要性
さらに議員は、国の地球温暖化対策推進法に基づく「地方公共団体実行計画」には「事務事業編」と「区域施策編」があり、後者は市町村に努力義務があることを指摘。愛川町としても区域施策編を策定し、町全域での温室効果ガス削減を具体的に推進すべきではないかと求めた。
4.6 クールチョイスとデコ活の違い
議員は「町民への説明のためにも、クールチョイスとデコ活の違いを分かりやすく」と再質問。環境課長は、クールチョイスが「省エネ・低炭素製品の選択を促す運動」であるのに対し、デコ活は衣食住や移動・仕事・買物など生活全般の行動変容を促し、より具体的かつ包括的な国民運動であると答弁した。
4.7 啓発活動の提案
最後に岸上議員は、町民への周知・啓発の強化を提案した。
町HPやSNSで積極的に発信すること。
「ふるさとまつり」の既存ブース(フードドライブ等)と連携してデコ活を紹介すること。
各種セミナーや集会で取り上げ、町民に「自分事」として捉えてもらう工夫をすること。
「町民一人ひとりが自らの行動を変えることが、脱炭素実現の最大の力となる」と述べ、第1項目を締めくくった。
5. 議論の総合評価
今回のやりとりを整理すると、以下の点が浮かび上がる。
町の施策は公共施設、省エネ補助、森林整備、リサイクル事業と幅広く展開しており、年々実績が拡大している。
町長によるゼロカーボンシティ宣言は、今後の方向性を示す重要な意思表示である。
岸上議員は、町民が実感できる施策(省エネ家電補助など)や広報活動の充実を強調。
区域施策編の策定提案は、町が今後さらに広域的・具体的に施策を進めるための課題を提示した。
クールチョイスからデコ活への切替を、町は11月を目途に進める考えを明言した。
6. まとめ
愛川町の地球温暖化対策は、町自らの努力(公共施設省エネ化・森林整備)、町民への支援(補助金・リサイクル制度)、国の政策への対応(ゼロカーボンシティ宣言・デコ活切替)という三層構造で進められている。岸上議員はこれに対し「町民参加型の具体施策」や「情報発信強化」、「区域施策編策定」といった視点から更なる拡充を提案した。
このやりとりは、単なる環境施策の検証にとどまらず、町全体としてどのように「脱炭素社会」へ歩を進めるかを考える上で、重要な議論であったといえる。

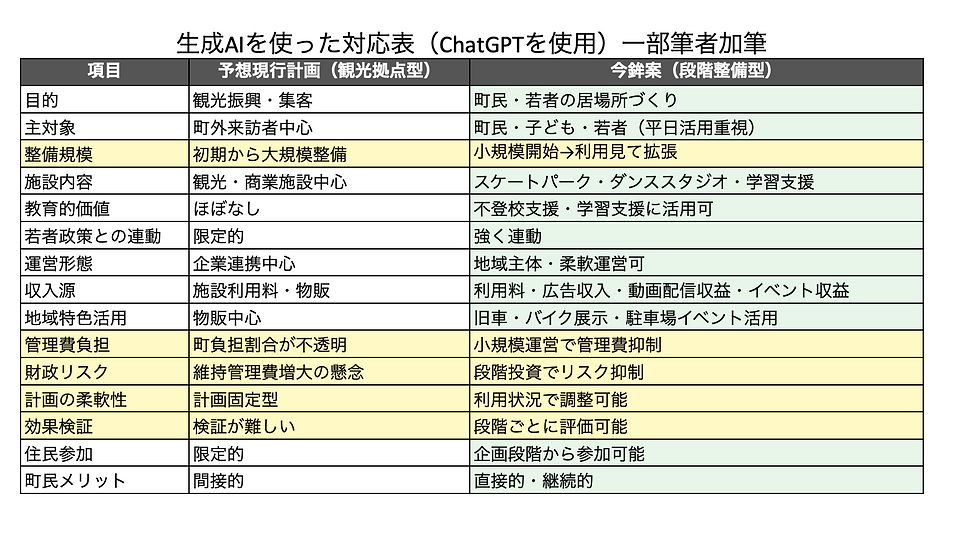


コメント